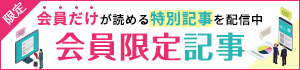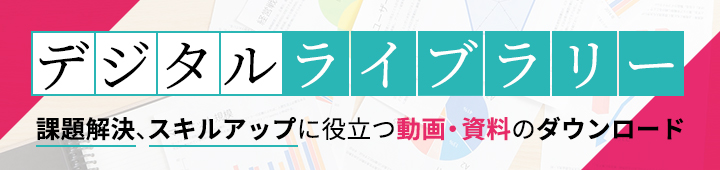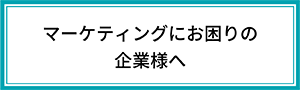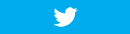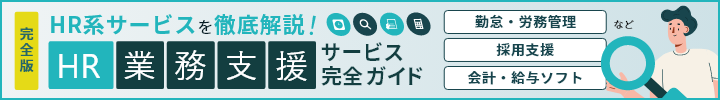日本で働く外国人 匿名座談会【前編】
「空気読め」のハードルを超えろ?! 日本で働く外国人のホンネ
![]() 2019.04.03
2019.04.03

日本で働く外国人の数は年々増加している。グローバル化やダイバーシティの取り組みにより、外国人雇用を積極的に進める企業も増えてきている。さらに、2019年4月に施行を開始した改正入管法により、外国人労働者数はさらに拡大することは明白だ。
※参考:人事担当者が知っておくべき改正入管法と外国人雇用のポイント
では、実際に日本で働いている外国人は、日本の企業や働き方についてどう思っているのだろうか? 匿名であることを条件に、日本で働く外国人の方々に思いの丈を存分に語ってもらった。
※参考:
入管法改正に物申す。外国人の視点から見る日本の「働き方改革」
◆座談会参加者プロフィール
・王さん(仮名)
中国生まれ。中国の外国語大学で日本語を学んでから日本に留学、修士課程修了後、
日本の中小企業に就職。現在は大学生のキャリア形成支援に携わる。
・クマールさん(仮名)
インド生まれ。インドの大学院を卒業後、日本の大手メーカーに就職。
映像技術の研究開発に従事する。
・@人事編集部M
日本生まれ。生粋の日本人。
旅行以外の海外経験はなし。英語もからっきし。
外国人が持つ日本のイメージは「年功序列」「仕事熱心」
@人事編集部M(以下、編集部M):まずはお二人のお仕事内容を簡単に教えてください。
王さん(以下、王):大学生向けの就職活動支援のイベント運営と、キャリア教育のプログラムの企画運営を行っています。
クマールさん(以下、クマール):私はメーカーの映像技術開発部におります。新しい映像体験を提供するために、VRやARなど映像の先端技術の研究開発に取り組んでいます。
編集部M:お二人とも、日本語がとても流暢ですね。ところで、なぜ日本で働こうと思ったのですか? 何かきっかけがあったのでしょうか。
王:私は元々日本に興味があったので。外国語大学では日本語を専攻して、大学院に進学してからも日本のことをもっと深く知りたいと思い、「国際日本」を専攻しました。この6年間で身に付けた日本語スキルをもっと磨きたくて、日本で働くことにしたのです。
クマール:私は特に日本で働きたいと思ったわけではなくて、入社したいと思った会社がたまたま日本の会社だったんです。就職活動の時期に、現在勤務している日本のメーカーが、わざわざインドに来て新入社員を募集しているのを知りました。求人内容を見て、私が大学院で研究していた専門領域とぴったりだったので、応募しました。無事採用され、日本に来たわけです。
編集部M:日本に来てみて、どうですか? イメージとのギャップがあったりしました?
王:日本の会社は年功序列の考えが強いイメージでしたが、これはイメージ通りでした。私の周りでは、日本人は入社したら一生その会社で働くという傾向が強いですね。
編集部M:最近では年功序列制度を廃止する企業もありますが、まだまだ浸透していない部分も多いようですね。クマールさんは?
クマール:私だけではなく多くのインド人は、日本は技術的に進んでいて、日本人は仕事熱心というイメージを持っているのですが、これは全くその通りでした。自分のためだけではなく会社のために働く意識が強い。成果を出して会社に貢献したいという目的で働く社員が多くて素晴らしいと感心すると同時に、想像を上回る熱意に驚きました
一方で、インドもそうですが洋文化(ヨーロッパ文化)が浸透している国や地域では、人の特性や個性を大事にするんですが、日本はあまり大事にされないなと思ったことがあります。
王:イメージと違ったのは、人手不足の深刻さですね。日本に来て最初に勤めた会社では、外国人だろうが日本人だろうが関係なく、多くの業務を任されました。コミュニケーションがまだぎこちなかった頃だったので戸惑いながら仕事をこなしていましたが、そんなことは気にも留められず……皆さん忙しかったんですね。周りを気にかける余裕もなく、目の前の仕事に没頭していました。日本の人手不足がこれほどとは思っていませんでした。想像以上でした。
社員研修やジョブローテーション制度が好印象
編集部M:日本で働いて良かったと思うことは?
王:日本の企業は一度決めたら最後までやり抜く精神がすごいと思います。それと、日本企業のコミュニケーションの特徴である報告連絡相談、いわゆるホウ・レン・ソウが徹底されていて、素晴らしいと感じます。
編集部M:中国にはホウ・レン・ソウがないんですか?
王:現時点では、一般的な中国企業の多くは、日本のように徹底された考え方が足りないと言われています。それと、社員に仕事の手順ややり方を丁寧に教えてくれる。社員教育をしっかりしてくれるのも、日本で働いていて良かったと思うところです。
クマール:私も教育・研修制度が充実している点は良いと思います。今の会社ではいろんな研修が受けられて、ちゃんと成長を見守ってくれているという安心感があります。インドの場合、新入社員研修のようなものはなくて、入社後はさっさと仕事を始めて、仕事をする上で必要なことや分からないことは実戦で学んでいくスタイルなんです。
編集部M:確かに、日本では新入社員研修が普通ですが、それを手厚いと感じたことはなかったです。日本は恵まれているんですね。
王:日本はジョブローテーション制度があるのもいいと思います。他の国の会社ではあまりやりませんよね。
クマール:当社でも、社員に開発だけじゃなく製造までの全てのプロセスを学ばせるためにジョブローテーション制度があります。私も製造実習でさまざまなことを幅広く学び、視野が広がりました。人としても成長できるので、すごく良い制度だと思います。
編集部M:これもあまり特別なことだと思っていませんでした。なるほど。

「日本の企業は社員教育制度が整っている」と語る二人。
日本の会社しか知らない@人事編集部Mには意外な意見だった。
「結論から言うと」は日本のビジネスシーンならでは?
クマール:まだあります。日本の会社は何かのプロジェクトを実行するとき、決断が下されてからの動きがとてつもなく早い。王さんもおっしゃってましたが、ものすごいスピート感で最後までやり遂げる。ただ、決まるまでのプロセスが長いんですよね(笑)
編集部M:言われてみると、長いかも(笑)
クマール:アメリカやインドでは、仕事を効率的に終わらせるために、決断を早くする。早めに決断してすぐ作業に取り組むやり方が主流なんですが、日本はまず理屈から始まって全てのストーリーを説明して、それから結論を言うというプロセスを踏むことが多い。だから、日本に来て最初の頃は、先輩たちが使う「結論から言うと○○です」という表現に違和感があったんです。不思議な言い方をするなぁ、と。
編集部M:よく聞きますね。ビジネスシーンの話し方のコツ、のような。
クマール:なんでわざわざ前置きするのだろうと思ってたんですが、仕事の進め方を見るようになってから、納得しました。
編集部M:そう言わないと結論が出るまでが長いからですね。耳が痛いというか。
クマール:じっくり考えてから実行に移すというやり方なんですよね、日本は。善し悪しがあると思いますが、日本の企業の特徴だと思います。その後のスピードも含めて。
海外企業は成果主義 過去の貢献も評価に含まれず
王:日本の中小企業は従業員を家族のように思って面倒を見ますよね。社員が会社に守られているということが新鮮で、良いなと感じました。
編集部M:海外の企業だと社員の面倒を見るとか、守るというような考えはないのですか?
王:少なくとも一部中国のベンチャー・中小企業の場合はあまりないと友人からは聞いています(笑)。そのような中国企業で働く場合、若いうちに成果を出してどんどん出世しても、40~50代になった時に能力が落ちて成果を出せなくなると給料が上がらなくなったり、解雇されたりします。業績が悪くなったらその部門ごと切られることも珍しくありません。
編集部M:会社に貢献したという評価もないんですね。徹底していますね。
クマール:インドの企業もメリットベースなので、成果が出せなくなったらすぐ切られます。過去の貢献もあまり関係ないです。
編集部M:外資系企業はその辺りがシビアだという意見を聞きますが、日本が特殊なんですかね。
王:他の国は分かりませんが、労働市場の流動性が高く、即戦力を求める中国の民間企業と比べると人情的だと思います。
「空気読め」はムズカシイ! 察しろ文化の日本
編集部M:逆に日本で働いてみて大変だったことは何でしょう。
王:時間にものすごく厳しいことです。基本的に遅刻は厳禁で、遅刻する場合は事前にちゃんと連絡しなければならないことに、最初は戸惑いました。
編集部M:そういうものですか。
王:逆に、開始時間にはものすごく厳しい反面、終了時間にはルーズですよね。定時になってもなかなか帰れない雰囲気があったり。
編集部M:会議が長引くのが当たり前だったり。
王:それと、上下関係も厳しい。例えば、新人は早く出社して掃除をしたり、電話を取ったりしなければならない、とか。でも一番苦労したのはコミュニケーションですね。
編集部M:言語の問題で?
王:言語というよりも雰囲気ですね。忖度というか、阿吽の呼吸を求められるというか。「空気読め」とか「察しろよ」と言われることもあるのですが、なかなか難しい。日本独特の文化ですよね。
編集部M:先輩や上司に実際に「空気読め」と言われたことがあるんですか?
王:あります。以前勤めていた会社では、会議で新しいことを提案したり、相手とディベートすることはなかなかできませんでした。会議で採用される案は、事前にキーパーソンに根回しをして、全員の同意を得るという段取りを踏んでいます。つまり、会議をする前に、採用される案がすでに決まっているんです。だから会議の場で「その案はいかがなものか」と反対意見を言っても相手にされないし、会議が終わった後、上司から「空気を読め、変なことを言うな」とたしなめられたことがあります。
編集部M:絵に描いたような「日本の会社」ですね……。クマールさんは「空気読め」と言われたことは?
クマール:うーん、なくはないですね(笑)。と言ってもそのときではなく、後になってから「あのときは空気を読んでほしかったな」と軽く言われた程度ですが。そもそも空気を読まなければならない場には入らないようにしています。それでも、会議に参加しなければならないこともありますが、事前に「こういうことは言わないように」と釘を刺されます。

「空気を読む」という日本独特の風習。
言語スキル以上のコミュニケーションに悩む外国人は多いようだ。
本音と建前。日本人との付き合いには頭を使う
編集部M:日本人でも空気を読むことは難しいですよ。「空気読め」に苦労している外国人の方は多いのでは?
クマール:そうですね。自分を責めるタイプの人や、相談できる人がいない人は特に苦しんでいます。そもそも同世代の日本人はあんまり本心を言ってくれないので、相談しづらいんですよね。
編集部M:本音で話してるつもりでも、無意識に隠している部分があるかもしれません。コミュニケーションの問題は他にもありますか?
クマール:私の場合はあまりないのですが、別の部署ではTPOが分からなくて困っている外国人社員もいますね。その原因が言語の壁なのか、考え方の違いなのかは微妙なところですが。
王:本音と建前のギャップで困ることもよくあります。みんなで一緒にいるときはストレートに自分の感情を表すのはあまり良いことではないというか、TPOをわきまえて、その場にふさわしい発言をしなければいけないというのは、かなり気を使うので大変です。
クマール:まず頭の中で言語変換をして、その上でTPOを考えて発言する。結構ハイスピードで頭を使わなければならないんですよ(笑)
編集部M:それこそ察してほしいですよね。
日本で働くことの良さや苦労。日本企業の社員教育や育成に関しての評価が高く、反面、日本特有の社会や企業文化に悩まされる場面が多いようだ。
「空気を読む」を外国人に求める必要があるのかどうかはやや疑問だが、それでも日本で働くことは自身にとってメリットが大きいと、二人は語る。
後編では、日本の「働き方改革」や外国人を雇い入れる企業について、お二人に意見を聞く。
■日本で働く外国人 匿名座談会【後編】はこちら
入管法改正に物申す。外国人の視点から見る日本の「働き方改革」
【編集部より】
■関連記事はこちら
@人事では『人事がラクに成果を出せるお役立ち資料』を揃えています。
@人事では、会員限定のお役立ち資料を無料で公開しています。
特に人事の皆さんに好評な人気資料は下記の通りです。
下記のボタンをクリックすると、人事がラクに成果を出すための資料が無料で手に入ります。
今、人事の皆さんに
支持されているお役立ち資料
@人事は、「業務を改善・効率化する法人向けサービス紹介」を通じて日本の人事を応援しています。採用、勤怠管理、研修、社員教育、法務、経理、物品経理 etc…
人事のお仕事で何かお困りごとがあれば、ぜひ私達に応援させてください。

「何か業務改善サービスを導入したいけど、今どんなサービスがあるのだろう?」
「自分たちに一番合っているサービスを探したいけど、どうしたらいいんだろう?」
そんな方は、下記のボタンを
クリックしてみてください。
サービスの利用は無料です。
関連記事
-
 企画
企画【INTERVIEW】株式会社CFPコンサルティング 坂牧毅 氏
プロフェッショナルな人材を正しく評価する仕組み~CFPコンサルティングの人事評価制度
「なんとなくいいこと」ではなく「確実に成果を出す行動」を評価する——。多くの企業が人事評価制度の見直しに苦心する中、CFPコンサルティングは「結果にコミットする」評価基準を確立した...
 2025.05.09
2025.05.09 -
 企画
企画令和の福利厚生を探る
従業員のモチベーションを高めるミズノの企業ユニフォーム「WORK WEAR」とは?
熾烈な人材獲得競争や従業員のエンゲージメント向上が課題となる近年、企業のユニフォームは単なる作業着ではなく、福利厚生や企業ブランディングの重要な要素へと認識が変わってきた。スポーツ...
 2025.04.23
2025.04.23 -
 企画
企画【INTERVIEW】株式会社ベンチャー広報 三上毅一 氏
メディアと企業をつなぐ架け橋 ~広報のプロが語る「取材獲得への5ステップ」
人事や総務を担当する一方で、広報業務も兼務している担当者は少なくない。特に中小企業やスタートアップでは、限られたリソースの中で効果的な広報活動を行うことが求められている。しかし、メ...
 2025.04.21
2025.04.21
あわせて読みたい
あわせて読みたい

 人気の記事
人気の記事

 国内・海外ヘッドライン
国内・海外ヘッドライン

 THE SELECTION
THE SELECTION
-
 THE SELECTION特集
THE SELECTION特集【特集】ChatGPT等の生成AIが一般化する社会で必須の人材戦略・人的資本経営の方法論
-
 THE SELECTION企画
THE SELECTION企画人事のキャリア【第25回】
皆がうらやむような会社づくりに取り組む(アイロボットジャパン・太田浩さん)
-
 THE SELECTION企画
THE SELECTION企画レポートまとめ
@人事主催セミナー「人事の学び舎」 人事・総務担当者が“今求める”ノウハウやナレッジを提供
-
 THE SELECTION特集
THE SELECTION特集「副業」新時代-企業の向き合い方 特集TOP
-
 THE SELECTION特集
THE SELECTION特集人事のキーパーソン2人が@人事読者の「組織改革」の疑問に答えます(第2弾)
数値化できない部署を無理に人事評価する方が問題。曽和利光×北野唯我対談
-
 THE SELECTION特集
THE SELECTION特集「令和時代に必須! ハラスメント対策最前線」
パワハラと指導の違いは? 6種類のパワハラを佐々木亮弁護士が徹底解説(中)