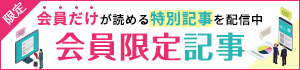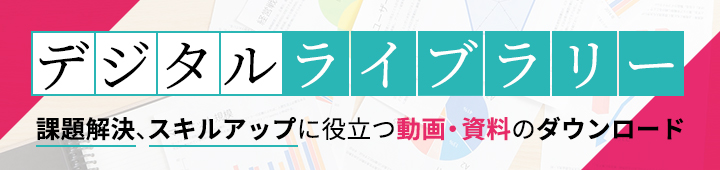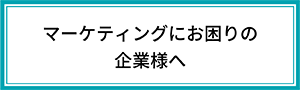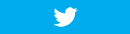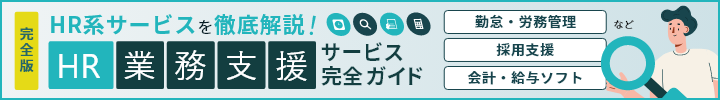人事のキャリア【第27回】
人材育成のノウハウを生かす自衛隊出身のIT企業人事(デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 山下隆康さん)
![]() 2025.03.31
2025.03.31

人事のキャリアは、業界や企業ごとに多様でありながら、共通する課題も多く存在する。今回は、自衛隊出身の人事担当者として活躍するデジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社(DIT)の山下隆康氏が登場。独自の人材育成メソッドで組織を変革し、採用戦略を成功させてきた。「足で稼ぐ」情報収集から組織全体を俯瞰した戦略的思考まで、自衛隊時代の経験を企業の人材育成にどのように生かしているのか。異色の経歴から生まれた独自の人事手法をひもとく。【取材・構成:編集部】
関連記事:これまでの「人事のキャリア」。
山下 隆康(やました・たかやす)
管理本部 人財企画部
1985年に防衛大学校を卒業し航空自衛隊入隊。戦闘機パイロット、航空幕僚監部運用課、航空幕僚監部防衛課を経て、2001年に米国防衛駐在官。2005年以降、在日米軍再編問題やイラク復興支援空輸計画に携わる。2012年に第11飛行教育団司令兼静浜基地司令として本格的に人材育成に関わり、2014年に統合幕僚学校教育課長として高級幹部の人材育成の責任者を務める。その後、2016年に防衛研究所軍事戦略研究室長を務め、2019年2月に退官。DITへ入社。
パイロットよりも人材育成のプロとしての経験を生かす道を選択
──自衛隊から現在の会社に入社されたという経緯について教えていただけますか。
自衛隊では現役で働いている間は就活ができない決まりになっているんです。このため、定年の3年ほど前に、エントリーシートのようなものを書いて支援部署に提出します。そこで本人の希望や適性を加味して、合いそうな会社を紹介してくれる仕組みになっています。私は自衛隊時代に飛行機を操縦する仕事をしており、外国勤務も多かったのでパイロットや商社などの話もあったのですが、すべて単身赴任が前提でした。現役時代も何度か単身赴任を経験しましたので、定年後までそれが続くのは避けたいと思いました。
そこで他の選択肢をお願いしたところ、DITを最初に紹介されました。飛行機に乗るわけでも外国人と話すわけでもない仕事に最初は不安を感じましたが、人事の仕事、特に採用や育成が主な業務と聞き、これなら自分の経験が生かせると思いました。自衛隊での仕事内容とは全く違いますが、本質的に近いところがあると感じたんです。
また、「この会社は面白い」と思えたことも大きいですね。創業社長が「基本的な考え方は本社で決め、実行は現場に任せる」という米軍の先端的な運営方針に近い考え方を自ら考案し、実行されていたことに感銘を受け、このような会社で働きたいと思いました。
──自衛隊時代から人材育成は得意なことだったのでしょうか。
自衛隊では、有事に備えた人員補充や人材育成が重要視されているので、「いかに効率的・効果的に人を育てるか」が、最大のテーマの一つとなっています。私自身も、30歳くらいの時にアメリカ空軍との交換協定でF15戦闘機の操縦や戦技をアメリカ人に教えるという経験もしました。その時にアメリカ流・NATO流の教育方法を学び、それを持ち帰って自衛隊で普及させたりもしています。
足で稼ぎ、戦略的に行う採用活動

──現在はどのような業務を担当されていますか。
新卒社員の採用活動を主体に、並行して担当する研修の準備、講師、分析などを行っています。
──採用活動は戦略的に行っていると伺いました。
自衛隊ではどこでもやっていることですが、前年度の計画と結果を振り返り、成功と失敗を分析し、次年度に何を変えるべきかを考えるという年度の振り返りが必ずあります。それに基づいて次の年度の戦略と計画を立てていく。このPDCAサイクルをずっとやってきました。
例えば、DITは世間にあまり知られていない企業でした。採用人数も年に40人程度でしたが、会社を大きくしたいという要望に基づき、なんとか応募者数を増やす努力をしました。
マイナビやリクナビに社名を載せても、「B to B」の会社は学生にはなかなか認知されていません。そこで思いついたのが、直接専門学校や大学に行って売り込むという方法です。キャリアセンターに企業情報が山のようにある中で、担当の先生から「こういう会社もあるよ」と紹介してもらえれば状況が変わると思ったのです。このアプローチを始めてから応募者は2倍以上に増えました。
6月から7月にかけて、内定承諾をいただいた方の学校を中心にお礼に訪問し、10月から11月ごろ「来年もよろしくお願いします」という挨拶で再度伺うのですが、年間で100校以上は訪問していますね。地方にも足を延ばしていて、時には1日に4校訪問することもあります。「足で稼ぐ」ことを信条にしているので、1カ月半で50 校ほど訪問することも苦になりません。
研修体系を一から構築

リーダー研修で講師を務める 山下さん
──もう1つの担当である、研修はどのように行っていますか。
私が入社した当時は新人研修以降の体系的な研修システムがなかったので、すべて自分の発想で構築しました。私が入社後、エンジニアをはじめとするさまざまな人と交流する中で、彼らのポテンシャルの高さを感じ、それを最大限に引き出すためには組織の骨格となるリーダーの育成が重要だと考え、リーダー研修をはじめとする体系的人材育成システムを構築しなければと思いました。
最初から、構築しようと思う研修システムの全体像を見せても賛同してもらえないと考え、初級リーダー研修から始め、成果を見せながら中級、上級へと広げていくことにしました。
まずは現場のリーダーを対象とした初級リーダー研修を計画し、その具体的な内容と期待される成果を直属の上司である人財企画部長とその上の管理本部長に説明しました。管理本部内での実施を承諾いただき、「成果が出せるのであれば全社に展開しても良い」と言っていただけました。条件付きではありましたが、とりあえずの実施の許可を得ることができたのです。その結果、この研修の評判が非常に良く、本格的な研修の開始を許可されたという訳です。
研修を実施したあとは、受講者にアンケートを取って、「こんな評価・評判です」と伝えることで会社から徐々に理解を得ました。2年ほど経つと「現場だけで良いのか」という声が出始め、部長などを対象とする中間管理職の研修やカンパニー社長らを対象とする上級管理職の研修も実施するようになったのです。
私が工夫した点は、アンケートを記名式にしたことです。アンケートは本音の意見を言い易くするために無記名にすることが多いようですが、研修内容が本当に理解されたときには記名式であっても本音のフィードバックが得られる、記名式にも関わらず本音の意見が得られれば説得力が大いに増すはずだと考えたのです。
「自分の上司はチームをまとめるのに苦労しているが、この研修の内容を教えたら楽になるのではないか」といった非常に具体的な意見も出てきています。このように研修を行った後には必ずアンケートを取り、率直な意見をもらって改善点を見つけています。自衛隊の研修では、初級でも約3カ月、中級では1年かけて行うのですが、それを1日に凝縮しているので、どうしても詰め込みになったり言葉足らずになったりする部分があります。そういう意見を参考にしてブラッシュアップを図っています。
フォロワーシップの重要性
──研修の効果はどのように感じていますか。
例えば、初級リーダー研修を受けた人がOJTトレーナーとして新人を指導する際に、研修で学んだ知識を活用しているのを見ると、効果が出ていると感じます。また、中級リーダー研修を受けた人の部下が初級リーダー研修を受け、「上司がこんなことを言っていたのは、山下さんの講義のこの部分から来ているのではないか」などと話してくれた時には、少しずつですが、研修の効果が組織に浸透していると感じています。
経営層からも「中級リーダー研修をもっと強化してほしい」というリクエストをいただき、部長以上の昇進には中級リーダー研修の受講が必要になるなど、研修の重要性が認められてきています。組織全体がどう変わっていくかは5年、10年かかるため、まだ明らかな成果は見えていませんが、小さな変化が少しずつ見えてきているのが嬉しいですね。
──研修の際に重要視しているという「フォロワーシップ」について詳しく教えてください。
企業の中でフォロワーシップという言葉自体があまり知られていませんが、人材育成においては非常に重要です。フォロワーシップとは自分の立場をしっかり理解した上で、上司に対して積極的に意見を述べ、提案していく姿勢のことです。若い人たちが言われたことだけをするのではなく、自らの頭で考え意見やアイデアを出していくことで会社が活性化します。
上司の立場からも、部下がただ言われたことだけをするよりも、それぞれが「こうした方が良いのではないか」と意見を出し合う方が、チームとしての成果が向上するのです。
また、リーダー研修というと、組織を「どう引っ張っていくか」だけを教えるイメージがありますが、社長以外は全員「上を支える」という役割もありますので、初級リーダー研修においても中級リーダー研修においてもフォロワーシップの内容をきちんと説明しています。
──人材育成における理想的な形とはどのようなものと考えますか。
仕事の能力の習得や伸びへの影響は、現場での体験が7割、知識が1割、上司の指導が2割と言われています。研修では必要な知識を提供し、それを踏まえて現場で経験を積む。その際、上司の指導によって進むべき方向が定められ、怠けそうになりそうなところを励まされる。このようにして能力が向上します。
理想的には、まず研修で知識を得て、ケーススタディなどで知識を自分のものとし、上司の指導を受けながら実務をこなして身につけていくという流れが理想的だと思います。
人事の知識も足で稼いで、人の話を聞くことで高める

──貴社の人事担当者のキャリアパスやキャリアモデルはどのようになっていますか。
人事担当者は新卒よりも中途入社の方が多く、エンジニアとして現場で働いていた人が途中から人事に異動してくることもあります。そのため、その人の素養に応じたオーダーメードのキャリア形成が必要になります。
ある人はアシスタントから始めて手取り足取り教える必要がありますが、別の会社から来た人は当社のことを理解すれば、すぐに説明会ができるようになったりします。個別に担当者を決めて、その人向けのプランを作っていくという形です。
今後は、技術系のキャリアパスと整合の取れた人事ローテーション(数年現場で働いて人事になり経験を積んで、また現場に戻るなど)を構築していきたいと思っています。2019年には40人程度だった採用人数が今は100人くらいになり、人事部門も大きくなりつつあるので、将来的にはもっとしっかりした体制にしていく必要があると思います。
──山下さんは普段、人事担当者として、どのような勉強をされていますか。
採用担当としては、今の世の中がどうなっているかという情報収集が重要です。マイナビやリクナビのセミナーに参加したり、学校訪問で各校の状況を自分で確かめたりしています。例えば「25年度入社の就活状況はどうですか?」と聞くと、学校ごとに違いはあるものの、世の中の大きな流れが見えてきます。その中で当社に欠けている部分を把握できるんです。
また、学校によっては採用担当者だけを集めたセミナーや情報交換会を開催しくれるところもあり、そういう場に積極的に参加して情報を得ています。
また、研修担当としては、これまでの経験をどうやってこの会社で生かせるかを考えています。人材育成の最先端は軍隊にあると考えており、そこで培ったノウハウをどう活用するかを工夫します。時には防衛省に情報収集に行くこともありますし、教育のプロである自衛隊の知人から防衛秘密に関わらない範囲でアドバイスをもらうこともあります。本を読んだりセミナーを受けたりするのも大切ですが、人から直接話を聞いて学ぶことの影響はものすごく大きいと思います。
──現在の業務を行う中で感じている課題はありますか。
採用においては、「過去と戦っている」状態だと感じています。前年の分析に基づいた対応はできていますが、次年の戦略しか考えられていないため、もう少し先の5年、10年を見据えた「未来への戦略」が必要だと感じています。
例えば、非連続的な変化が起きた場合の対応についても、シナリオプランニングなどの手法を使って準備しておきたいですね。コロナ禍では急遽オンラインを活用した面接・説明会に移行せざるを得ませんでしたが、パンデミックの可能性を想定して準備しておけばよかったと反省しています。また、インターンシップ制度の変更など、制度変更に対してもアンテナを張り、「万が一こうなったらどうするか」という準備をしておきたいです。
研修面では、自衛隊の場合、初級研修に3カ月、中級研修に1年、上級研修に1年かけますが、これは理論説明のみならず、その知識を定着させるために、ケーススタディなどを行ったり、実際に管理職として勤務する人の話を聞いたり、現場研修などを行ったりするための時間が含まれているためです。これに比べ当社の研修では理論説明が中心で、定着のための実習が不足しています。長期間の研修を行うことはなかなか難しいですが、今後は知識を定着させるためのeラーニングなどの仕組みを整えたいと考えています。
組織を成長させるためリーダー育成に尽力したい
──人事の仕事でやりがいを感じる部分は何でしょうか。
一番モチベーションになるのは、やった成果が目に見えることですね。
採用であれば、カンパニーから今年の新入社員は優秀だなどといった声が聞こえてきたり、目標人数が達成できたりなど、成果が目に見えた時はうれしいですね。研修については成果が見えにくいですが、研修で教えたことが実際に現場で活用されていたり、「上司の指導の中に研修の内容を見た」「この研修はお金を出しても受けるべきだ」といったアンケートの回答を目にしたりすると、やりがいを感じます。
──最後に、山下さんのように、異なる分野から人事になる方へのアドバイスをいただけますか。
会社によって人事の仕事は全く異なりますが、一番重要なのは「何が問題なのか、その本質を見極めること」です。問題の本質が見えれば、それを解決する手法は会社や環境に応じて考えられます。自分で気づけない場合は、優れた先輩や上司、同僚に相談することも大切です。社内で信頼できる人との関係をしっかり築いておくことで、さまざまな視点から問題を捉えることができるようになります。
──ありがとうございました。
山下さんのある日のスケジュール
7:00 起床後に朝食を食べ、出勤します。
8:30 出社。徒歩10分ほど。
9:00 業務開始。時期により面接、説明会、大学訪問をします。
12:00 昼食。
13:00 午前中と同じく、時期により面接、説明会、大学訪問をします。
17:00 本日行った業務のまとめ作業をします。報告書を作成したり、業務上で気付いたことをまとめたりしていきます。
17:45 終業。帰宅準備をしてまっすぐ家へ帰ります。
19:00 夕食、入浴、読書
22:00 就寝
山下さんの主な年間スケジュール
企業情報

デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社
・事業内容:ソフトウェア開発事業(ビジネスソリューション事業、エンベデッドソリューション事業、プロダクトソリューション事業)
・本社所在地:東京都中央区
・設立年:2002年1月4日
・従業員数:1,499名(連結)(2024年6月末現在)
・企業URL:https://www.ditgroup.jp/
※情報は2025年3月末時点
【参考】「人事のキャリア」シリーズ一覧
@人事では『人事がラクに成果を出せるお役立ち資料』を揃えています。
@人事では、会員限定のお役立ち資料を無料で公開しています。
特に人事の皆さんに好評な人気資料は下記の通りです。
下記のボタンをクリックすると、人事がラクに成果を出すための資料が無料で手に入ります。
今、人事の皆さんに
支持されているお役立ち資料
@人事は、「業務を改善・効率化する法人向けサービス紹介」を通じて日本の人事を応援しています。採用、勤怠管理、研修、社員教育、法務、経理、物品経理 etc…
人事のお仕事で何かお困りごとがあれば、ぜひ私達に応援させてください。

「何か業務改善サービスを導入したいけど、今どんなサービスがあるのだろう?」
「自分たちに一番合っているサービスを探したいけど、どうしたらいいんだろう?」
そんな方は、下記のボタンを
クリックしてみてください。
サービスの利用は無料です。
関連記事
-
 プレスリリース国内・海外ヘッドライン
プレスリリース国内・海外ヘッドラインデジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社
中規模企業向けのセキュリティ商材に追加料金なしでサイバーセキュリティ保険を自動付帯する新サービスの提供開始
デジタル・インフォメーション・テクノロジー(東京・中央)は3月31日、サイバーセキュリティ対策の統合基盤「DIT Security Platform」の提供を開始した。「DIT S...
 2025.04.01
2025.04.01 -
 企画
企画人事のキャリア【第26回】
急成長するIT企業で人材採用の最前線に立つ (アルサーガパートナーズ・青山哲也さん、高橋歩さん)
さまざまな業種の人事担当者に、これまでのキャリアや仕事のやりがいについてインタビューする連載企画「人事のキャリア」。今回伺ったアルサーガパートナーズ(本社:東京・渋谷)は、「日本の...
 2024.09.03
2024.09.03 -
 THE SELECTION企画
THE SELECTION企画人事のキャリア【第25回】
皆がうらやむような会社づくりに取り組む(アイロボットジャパン・太田浩さん)
注目の外資系企業のHRビジネスパートナーとして働くさまざまな業種の人事担当者に、これまでのキャリアや仕事のやりがいについてインタビューする連載企画「人事のキャリア」。今回はロボット...
 2021.08.10
2021.08.10 -
 企画
企画【INTERVIEW】株式会社CFPコンサルティング 坂牧毅 氏
プロフェッショナルな人材を正しく評価する仕組み~CFPコンサルティングの人事評価制度
「なんとなくいいこと」ではなく「確実に成果を出す行動」を評価する——。多くの企業が人事評価制度の見直しに苦心する中、CFPコンサルティングは「結果にコミットする」評価基準を確立した...
 2025.05.09
2025.05.09 -
 企画
企画令和の福利厚生を探る
従業員のモチベーションを高めるミズノの企業ユニフォーム「WORK WEAR」とは?
熾烈な人材獲得競争や従業員のエンゲージメント向上が課題となる近年、企業のユニフォームは単なる作業着ではなく、福利厚生や企業ブランディングの重要な要素へと認識が変わってきた。スポーツ...
 2025.04.23
2025.04.23 -
 企画
企画【INTERVIEW】株式会社ベンチャー広報 三上毅一 氏
メディアと企業をつなぐ架け橋 ~広報のプロが語る「取材獲得への5ステップ」
人事や総務を担当する一方で、広報業務も兼務している担当者は少なくない。特に中小企業やスタートアップでは、限られたリソースの中で効果的な広報活動を行うことが求められている。しかし、メ...
 2025.04.21
2025.04.21
あわせて読みたい
あわせて読みたい

 人気の記事
人気の記事

 国内・海外ヘッドライン
国内・海外ヘッドライン

 THE SELECTION
THE SELECTION
-
 THE SELECTION特集
THE SELECTION特集【特集】ChatGPT等の生成AIが一般化する社会で必須の人材戦略・人的資本経営の方法論
-
 THE SELECTION企画
THE SELECTION企画人事のキャリア【第25回】
皆がうらやむような会社づくりに取り組む(アイロボットジャパン・太田浩さん)
-
 THE SELECTION企画
THE SELECTION企画レポートまとめ
@人事主催セミナー「人事の学び舎」 人事・総務担当者が“今求める”ノウハウやナレッジを提供
-
 THE SELECTION特集
THE SELECTION特集「副業」新時代-企業の向き合い方 特集TOP
-
 THE SELECTION特集
THE SELECTION特集人事のキーパーソン2人が@人事読者の「組織改革」の疑問に答えます(第2弾)
数値化できない部署を無理に人事評価する方が問題。曽和利光×北野唯我対談
-
 THE SELECTION特集
THE SELECTION特集「令和時代に必須! ハラスメント対策最前線」
パワハラと指導の違いは? 6種類のパワハラを佐々木亮弁護士が徹底解説(中)