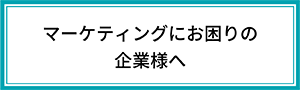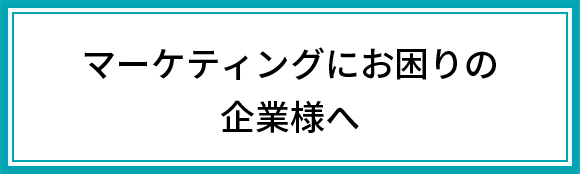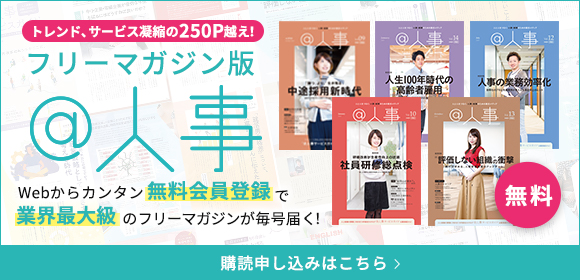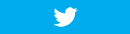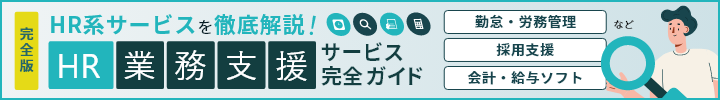特定技能雇用を行う企業側の課題(体制・意識)と今後の外国人雇用動向予想【後編】
外国人材雇用における企業の課題2

BEENOS HR Link株式会社代表取締役社長の岡﨑 陽介が特定技能制度の成り立ちから課題点、これからの展望などを実際の例を交えながら紹介する本連載。前回は外国人材雇用における企業の課題について外国人材雇用に対する企業意識などについて紹介しました。第四回後編となる今回は引き続き外国人材雇用における企業の課題にフォーカスし、特定技能に関する企業の意識や外国人材の採用プロセスにおける課題などについて解説します。
前回:外国人材雇用における企業の課題1
連載記事:https://at-jinji.jp/expert/column/104
目次
外国人材を雇用するうえでの企業の意識の現状
外国人材を雇用する企業の中には、制度や支援内容について十分に理解していないケースがまだ見受けられます。「特定技能」という制度の存在を知っていても、その具体的な内容や手続きの手順については把握が不十分という事例も少なくありません。
例えば、外国人材をすでに雇用しているにもかかわらず、制度の詳細を正確に理解できていないという例や特定技能を技能実習制度と混同している例もあります。制度の理解が十分でないことによって結果として受け入れ企業が適切な体制を整えられずに意図せず制度のルールに反する対応をしてしまうことがあります。そういった経緯を経て是正のためにBEENOS HR Linkにサポートとしてコンサルティングを依頼する企業もいらっしゃいます。
特に多い相談内容として、「特定技能について入口から教えてほしい」という要望があります。具体的には、「自社が外国人材を雇用できるのか」「どのような体制や手順が必要なのか」といった「まず何をしたら良いのかが分からない」ことによる質問です。
また、企業側が制度について理解していると思っていても、実際に詳細な手順や支援内容を問われると不安が残り、結果的に相談に至るといったケースもあります。
受け入れ企業にとっては就労時の手続きや申請・届け出や生活全般の支援など、外国人材の受け入れに関わる支援内容が幅広いため、どこから手をつければ良いかわからないという声も少なくありません。特定技能外国人の雇用を実際に開始する前に、特定技能での採用から雇用管理までの一連の流れを把握することが重要です。
特定技能の制度開始から数年たった現在では特定技能に特化した書籍やウェブサイトなどで情報入手は可能になっており、基本的な制度理解をするうえでは有用ですが、これらの情報は受け入れ企業の個別の事例に対応したものではないため十分な情報源とは言えないことがあります。
制度理解に十分なリソースを割くことが出来ない場合は受け入れ企業の規模感やコスト感に合わせて、行政書士や登録支援機関をはじめ、特定技能に関する知見を持った団体や企業との連携を検討することも必要になります。
.jpg)
外国人材の採用プロセスにおける課題
外国人材の採用プロセスにおいてよく見られる課題としては、採用方法と国ごとのルール、この2つの違いに対する理解が十分でないことが挙げられます。
採用活動を自社で行うか、エージェントに依頼するかでプロセスが大きく異なります。自社で行う場合、現地での採用、日本国内にいる外国人の採用など、状況によって必要な手続きや流れが変わります。一方、エージェントに依頼する場合は、どのエージェントに依頼するかが重要な課題となっています。BEENOS HR Linkが支援する企業の中には採用の前に良いエージェントがいないか紹介を求めるケースもあります。
さらに、外国人材の採用ルールは国によって大きく異なります。例えば、ベトナムでは現地エージェントを経由することが義務付けられており、その手数料を受け入れ企業、雇用される外国人材のどちらが負担するかが問題となりやすいです。ミャンマーでは、面接前に求職者が特定技能制度の対象であることを証明する許可が必要です。また、フィリピンでは、在日フィリピン大使館で受け入れ企業の社長などが直接面接を行う必要があります。
このように、採用方法と国ごとのルール、この2つの違いが企業の負担を増やしているのが現状です。これらの手続きの煩雑さが、採用プロセスをより複雑にしています。
このような状況の中、どの国の外国人材を採用するべきか、採用計画の初期段階から相談を持ちかける企業も増えています。採用プロセスにおける課題を解消するためには、各国のルールや必要な手続きについての知識を深め、企業ごとに適した採用チャネルや方法を検討するサポートが求められています。特に、多様な国の外国人材を受け入れるためには、受け入れ企業側に現地ルールに精通した専門的なアドバイスやサポートが欠かせません。
.jpg)
労働条件の不均衡とその原因
外国人材を雇用する企業において、日本人労働者との間に労働条件の不均衡が生じる要因の一つに、評価基準の認識のズレ が挙げられます。企業と外国人材がそれぞれ異なる基準で業務成果を捉えているため、評価が期待と一致しないと感じるケースが発生しやすいのです。
例えば、外国人材が「業務を正確に遂行しているにもかかわらず、評価が上がらない」と感じる場合、企業側は 顧客対応や職場内での円滑なコミュニケーションを重要な評価要素 として考えている可能性があります。これは外国人材に限った話ではなく、日本人従業員についても外食業などにおいてコミュニケーション能力の差が評価に影響を与えることは少なくありません。
特に、接客業やサービス業では、業務の正確性だけでなく、顧客とのスムーズなやり取りや臨機応変な対応が求められる場面も多いため、言語能力の面で不足がある場合、その分が評価に反映されにくくなることがあります。外食・宿泊・介護といった対人業務を中心とする業界では、言語スキルや接客品質が業務の一環とみなされるため、こうした評価のズレが生じやすいと言えます。
また、勤怠管理に対する意識の違いも、評価に影響を与える要因の一つです。時間厳守を重視する日本の労働文化と、柔軟な労働観を持つ外国人材との間で、勤務態度に関する認識のギャップが生まれることがあります。企業側が「勤怠のルールを守ることが職場の信頼関係の前提」と考えているのに対し、外国人材が「業務自体を問題なく遂行していれば評価されるべき」と捉えている場合、双方の期待が一致せず、不満の要因となることもあります。
さらに、言語や業務遂行能力に問題がなくとも、外国人材の話し方や表現方法が、日本人と異なるという理由で評価に影響を及ぼすケース もあります。企業側が無意識のうちに「ネイティブの日本人と同じようなコミュニケーションスタイル」を求めることで、外国人材が本来持つスキルや貢献度が正しく評価されないリスクが生じる可能性があります。
このような評価基準のミスマッチを解消するためには、企業と外国人材の双方が、評価の指標を明確に共有し、すり合わせを行うことが不可欠です。企業側は、評価基準を外国人材に対して具体的かつ明確に伝え、求められるスキルや期待値を理解してもらうことが重要です。一方で、外国人材も、企業の文化や価値観を踏まえた上で、自らの強みや改善点を意識し、適応していく姿勢が求められます。
適切なコミュニケーションとサポート体制を整備することで、双方が納得できる評価基準を確立し、公正な労働環境の実現につなげていくことが期待されます。
.jpg)
近未来における外国人材の役割拡大
日本における人口減少に伴い、今後ますます外国人材が活躍する機会は増大することが予測されます。特定技能や技術・人文知識・国際業務、留学生など、さまざまな形の在留資格で外国人材が労働市場に参入し、特に特定技能の受け入れも行っている人手不足が深刻な飲食料品製造業、工業製品製造業、介護、建設業などの様々な分野で重要な役割を果たすと予測されます。
企業にとって、外国人材は単なる短期的な労働力ではなく、長期的なキャリア形成を視野に入れたパートナーとして受け入れることが重要です。現在、日本における特定技能制度を介して雇用される外国人材の就労は特定技能1号による5年以内の勤務が主流です。特定技能に含まれる業種の多くはもともと離職率が高いところが多く、同一企業での5年間の継続勤務は、対象業種の平均勤続年数に比して決して短期とは言い切れません。企業によっては、この期間を一つのキャリアサイクルと捉えて雇用を行っていることもあります。
一方で、より長期的な就労を希望する外国人材も増えており、特定技能2号への移行を目指すケースも徐々に現れています。特定技能2号は、在留期間の上限がなく、引き続き専門性を活かして就労できる制度であり、制度の対象分野も拡大が見込まれています。そのため、外国人材が活躍する就労現場は今後も増加していくと考えられます。
外国人材の雇用がこれまで以上に一般化し、日本社会を形成する一員としてともに歩んでいくためには相互理解が不可欠となります。受け入れ企業は増加する外国人材に対して多様な支援を実施し、就労以外の場面でも外国人材が日本社会で安定して生活し出来るように支えとなり、これから日本で就労を希望する外国人材の良きロールモデルを作っていくことが必要です。外国人材についても日本文化への理解が重要となり、自身の持つ文化背景とのすり合わせや妥協点を模索することが時には求められます。コミュニケーションを通じて良好な就労環境を形成し、日本人と外国人材が相互に高めあい生産性に寄与する未来が期待されます。
>>>外国人材雇用の成功事例【前編】外国人材雇用で成果を上げるための企業のマインドと職場環境づくり
.jpg)
@人事では『人事がラクに成果を出せるお役立ち資料』を揃えています。
@人事では、会員限定のお役立ち資料を無料で公開しています。
特に人事の皆さんに好評な人気資料は下記の通りです。
下記のボタンをクリックすると、人事がラクに成果を出すための資料が無料で手に入ります。
今、人事の皆さんに
支持されているお役立ち資料