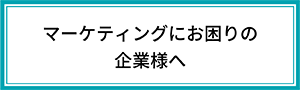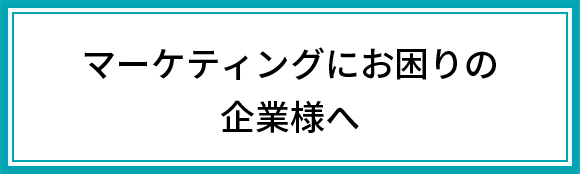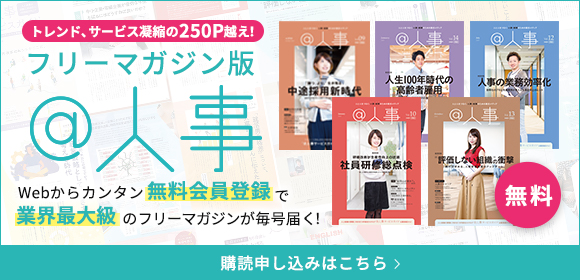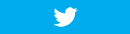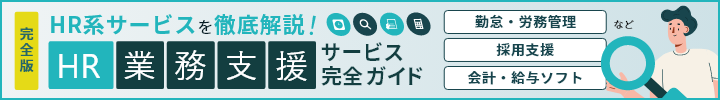外国人材雇用の成功事例【前編】
外国人材雇用で成果を上げるための企業のマインドと職場環境づくり

BEENOS HR Link株式会社代表取締役社長の岡﨑陽介が特定技能制度の成り立ちから課題点、これからの展望などを実際の例を交えながら紹介する本連載。前回は外国人材雇用における企業の課題について解説しました。
今回は外国人材雇用において成果を上げるための企業のマインドや、外国人材採用における職場環境づくりや雇用の成功事例などについて解説します。
前回:外国人材雇用における企業の課題2
連載記事:https://at-jinji.jp/expert/column/104
目次
外国人材雇用によって成果をあげるために企業が持つべき思考
外国人材を雇用する企業が成果を上げるためには、日本人従業員と外国人材が円滑なコミュニケーションを取れる職場環境を整えることが重要です。特定技能の雇用を行う企業の中には外国人雇用が初めてである企業も少なくないため、現場では言語や文化の違いからコミュニケーション不和が起こりやすく、それが生産性や職場の雰囲気に影響を与えることもあります。そのため、企業には双方の文化や背景を尊重した思考と取り組みが求められます。
例えば、Linkusを導入している企業でも、社員総会や勉強会、バーベキューといったイベントなどを通じて、従業員同士が親睦を深める機会を設けている事例があります。こうしたコミュニケーションが職場での人間関係を円滑にするひとつのきっかけにもなっています。就業以外の場面でコミュニケーションを取れることはメリットもありますが、一方で日本人であってもこういった交流の場が得意ではない人もいるように、外国籍人材も「交流の場さえあればOK」というわけでもありません。
大事なのは、双方の理解を深めるきっかけの部分を意識的に作っていくことです。外国人材が日本の環境に慣れるための支援や教育に注力するあまり、日本人従業員側への異文化理解などのサポートが盲点になっている場合もあります。
例えば、外国人材を雇用する際によく起こる問題の一つに、疑心暗鬼を生む職場内のコミュニケーション不和があります。日本人従業員同士が日本語のみで話したり、逆に外国人同士が第一言語で話したりすることで、「自分たちには分からないように陰口を言っているのでは?」といった不信感が生まれるケースがあります。
こうしたコミュニケーション齟齬による不和は日本人従業員同士でも起こりがちな問題です。何か問題が起きたときには積極的な話し合いを行い、解決するために双方が歩み寄ることを心掛けることで、こうした衝突を未然に防ぐことにつながります。日本人と外国人の双方を公平に指導し、互いを尊重したコミュニケーションを促すことで、外国人材雇用を成功に導ける企業といえるでしょう。
.jpg)
多文化共生を実現する職場環境作りの事例外国人材の採用プロセスにおける課題
外異なる文化や宗教を背景にもつ外国人材を職場に受け入れる際に、具体的にどのような対応が必要になるのかは、多くの方が気になることではないでしょうか?
ベトナムでは1月後半から2月初めごろにテトという旧正月のお祝いがあり、ベトナム国籍の方からこのタイミングで一時帰国したいという要望があります。こうした旧正月を祝う風習のある国出身の方から多い要望は、ベトナム以外の国でも聞かれます。
そのほか宗教上の理由として、外国人材がイスラム教徒の場合はメッカ巡礼などが挙げられます。メッカ巡礼は一生のうちに一度行けば良いという考えの人もいますが、特定技能で働いている期間内に行きたいということが発生する可能性もあります。
基本的にこうした文化や宗教を背景とした休暇の申請には企業は対応することが求められていますが、休暇取得のタイミングは企業側の状況も含めて調整が可能であるため、必ずしも特定技能外国人の希望通りにいかないこともあります。そのため、双方が納得できる形で一時帰国の休暇が取得できるように、コミュニケーションが重要になります。
長期休暇以外の例としては、イスラム教における定期的な礼拝や社食のハラル対応などがあります。礼拝についてはイスラム教では1日5回、15分程度の祈りをささげる時間と場所が必要です。企業によっては礼拝に使用する部屋を用意して、任意の時間で業務を抜けて礼拝できるように配慮を行っている事例があります。
しかし、すべてのイスラム教信者がそのように厳密に礼拝を行うわけではありません。宗教観については外国人材の世代によっても異なっており、特に若年層においては、礼拝はできるときにやれば良いという人や、5回分をまとめて一回で済ませるという人もいます。
ハラル食についても同様で、ハラルを厳密に守る人、お酒は飲む人などさまざまです。社食がハラル食に対応している事例はまだ一般的ではなく、自炊している外国人材が多く見られます。
企業による異文化・宗教への歩み寄りも大切ですが、特に若年層の世代の外国人材においては宗教観が変化していることもあるため、対話を通じて柔軟な対応が望ましいでしょう。
.jpg)
職場のコミュニケーション改善に成功した企業の取り組み
外国人材と日本人従業員の間には価値観や感覚の違いによってコミュニケーションがかみ合わないといった問題が起きることがあります。
例えば外国人材の中には時間間隔の違いから休暇申請の連絡を当日の始業時間をすぎてから行う人もいます。こうした労働観的な部分は日本人の場合「言わなくても分かるだろう」と考え、暗黙の了解になっていることで外国人材からは理解されにくくなっていることがあります。
また休暇申請について日本人の場合は「業務の繁忙との兼ね合いを考えて調整する」「年末年始や夏季休暇等の長期休暇のタイミングで休む」という意識が一般的ですが、そういった感覚がそもそもない外国人も実際は多くいます。そのため、日本における長期休暇が推奨される期間以外では「休みたいときに休めない」という外国人側からの苦情につながることもあります。
こういった課題に対してはBEENOS HR Linkでは日本文化を理解している通訳者に企業と外国人材の間に入ってもらうことで解決した事例があります。外国人材の母国と日本での事情を把握している通訳者から、細かなニュアンスを踏まえて慣習の違いなどを説明してもらえるとスムーズに理解が進みます。1回だけの対話では解決しないことが多いので、何度も対話を重ねる必要も時にはあります。
また、言語に関する課題も多くの方が気にされるポイントだと思います。Linkusを導入している飲食店で働いているベトナム国籍の方からは、就業現場でできる仕事が増えてきたことで、必要とされる日本語レベルが上がってきているが、まだ自身の日本語能力がそこまで及んでいないため悩んでいるという相談をいただくことがありました。
この相談者の場合は仕事を終えて帰宅してから十分に日本語の勉強の時間が確保できていないことが課題でした。そこで普段の生活の中で日本語に慣れるために、テレビ番組を流し聞きして日本語に慣れることや、目に入ったものを日本語でノートに書きとめるなどの対応を推奨することで、徐々に聞き取れるようになったという事例があります。
そのほか、先ほど触れましたが、職場での日本人同士・外国人同士のそれぞれの母語での会話が陰口に聞こえるなどコミュニケーション不和を招きかねない課題がある場合は、誤解を招く行為をしないように推奨してコミュニケーションが改善した事例があります。日本と海外の差異についての理解を企業と外国人材双方が深めることでコミュニケーションの改善につながっていきます。
.jpg)
企業の主戦力として活躍する外国人材の事例
外国人材は、企業の現場において重要な役割を果たし、業務の円滑化や質の向上に大きく寄与しています。Linkusを導入している企業の中には、外国人材が中心となり、店舗や現場を支える取り組みを実践している事例が多数見られます。
ここまで特定技能を介して外国人材雇用を行う際のさまざまな課題に触れてきましたが、こうした課題を乗り越え主戦力として活躍している外国人材の事例を紹介します。
例えば、飲食業では外国人材が新メニューの提案を行い、そのアイデアが採用され売上向上に貢献したケースがあります。また、外国人材が店舗運営の核として店長業務を担当している事例もあり、経営の一端を担う存在として活躍しています。
介護業界においては、外国人材の役割がさらに際立っています。例えば、夜勤で複数の部屋を一人で担当し、ワンフロアを任されるなど、高い責任感と実務能力が求められる仕事をこなしているケースがあります。このような現場では、外国人材の存在がなければ業務が立ち行かないほど必要不可欠となっています。特に介護という命に関わる仕事において、外国人材が信頼され、高い評価を得ている点は注目に値します。
これらの事例は、外国人材が単なる労働力ではなく、現場の課題を解決し、企業の持続的成長を支える重要なパートナーとして機能していることを示しています。企業が外国人材の能力を最大限に引き出す取り組みを続けることで、さらなる活躍が期待されます。
>>>「外国人材雇用における 成功事例【後編】外国人材の定着・活躍につながる 職場環境づくりのポイント」(4月3日公開予定)につづく
.jpg)
@人事では『人事がラクに成果を出せるお役立ち資料』を揃えています。
@人事では、会員限定のお役立ち資料を無料で公開しています。
特に人事の皆さんに好評な人気資料は下記の通りです。
下記のボタンをクリックすると、人事がラクに成果を出すための資料が無料で手に入ります。
今、人事の皆さんに
支持されているお役立ち資料