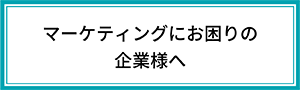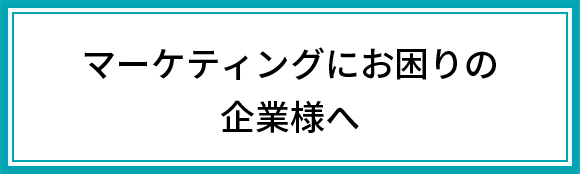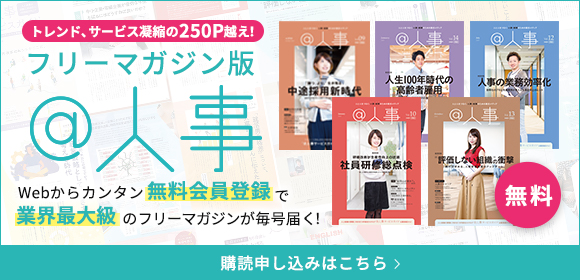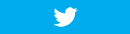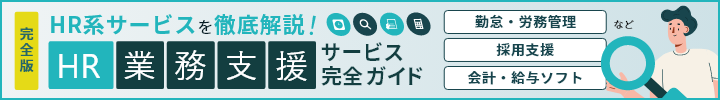外国人材雇用の成功事例【後編】
外国人材の定着・活躍につながる職場環境づくりのポイント

BEENOS HR Link株式会社代表取締役社長の岡﨑陽介が特定技能制度の成り立ちから課題点、これからの展望などを実際の例を交えながら紹介する本連載。前回は外国人材雇用において成果を上げるための企業のマインドや、外国人材採用における職場環境つくりや雇用の成功事例などについて解説しました。
今回は外国人材の定着・活躍につながる職場環境づくりのポイントについて解説します。
前回:外国人材雇用の成功事例【前編】外国人材雇用で成果を上げるための企業のマインドと職場環境づくり
連載記事:https://at-jinji.jp/expert/column/104
目次
適切な支援によって外国人材が活躍できる職場環境に
外国人材への業務指導においては外国人材の日本語レベルを考慮して難しくない日本語での声掛けが求められます。日本語ネイティブ同士で対話するときのような「言わなくても伝わる」といった要素を含まず、言葉を平易にゆっくり説明することが大切です。
日本人特有の「これやっておいて」のような指示語の入った曖昧な指示で次に何をすべきか分からない声掛けよりも、具体的な作業を依頼して「終わったら声を掛けて」と最初から最後までやるべきことを明確にした指示を行うことが効果的です。
また、現場業務では、業務を十分に理解していなくても「できる」と引き受けたり、本当は理解できていない業務を「分かる」と答えてしったりするケースが見られます。これは外国人に限らず、誰にでも起こり得ることです。こうした反応の背景には文化や環境の違いが影響することがあり、日本では「分からないことを質問する」「教えを乞う姿勢」が意欲的と評価される傾向があります。一方で、国や職場によっては、前向きな発言や自信を持った態度が評価されることもあります。
こうした感覚の違いについては、「理解できないことは必ずしも悪い評価にはつながらない」ということを外国人材に伝え、適切に指示を仰ぐことができる環境づくりが必要です。
また、日本人従業員からの外国人材への指示の際は『やさしい日本語』で話すことも重要です。ただし、丁寧語や謙譲語を多用すると、かえって難解になる場合があるため、平易な単語を用いた簡潔な表現が適しています。
「あれ」「それ」といった指示語を避け、主語を明確にすることも欠かせません。また、方言の使用を控えることで、コミュニケーションが円滑になります。これらの配慮が言語のハードルを下げ、外国人材がスムーズに業務に取り組む助けとなるでしょう。
.jpg)
外国人材のスキル向上を支援するための工夫
特定技能外国人が採用された場合でも、日本人従業員の新卒と同様に研修を行い、業務を学んでもらうことが一般的です。こうした日本語での説明や研修がある場合は、より日本語を嚙み砕いて説明したり、言語別のマニュアルを用意したり、研修用の動画を活用する企業の事例も見られます。日本人と同様に外国人材も現場に入ってから業務を教わることが多く、例えば飲食店では店長やバイトリーダーが指導を行いますが、技術習得までにどれくらい時間がかかるかは外国人材の背景やスキルによって異なります。
BEENOS HR Linkでは、新たに入社した外国人材への指導に、既に雇用されている先輩の外国人材にも加わってもらうことを提言しています。
先輩の外国人材がこれまで現場で教わったことを母国語に変換して後輩に指導することで、彼ら自身の理解が深まり、成長につながると考えています(ただし、日本語レベルを上げる目的を考える場合は、この方法は推奨しません)。
この取り組みは、リーダー的な立場の育成にもつながり、特定技能2号への転換を目指すうえでも重要な役割を果たします。さらに、こうした指導の循環が職場全体の活性化を促し、外国人材の定着率向上にも寄与することが期待されます。
.jpg)
外国人材と企業とのミスマッチをなくすためにできること
外国人材の雇用において、企業と外国人材とのミスマッチが生じることは少なくありません。
例えば、飲食店では外国人材の要望が店長に伝わるものの、店長では課題を解決できず、支援担当者に情報が届いた時点で既に退職が決まっているケースも見られます。こうした事態を防ぐためには、課題を早期に発見し、迅速に対応できる体制を構築することが重要です。特に外国人材の個別の相談を拾い上げられる仕組み作りが必要です。
また、宗教的な配慮が必要なケースもあります。
例えば、イスラム教徒の女性が着用するヒジャブが認められるかどうかは、職場によって異なります。飲食店や食品工場、介護施設では衛生面を理由に制服のみを着用する規定があることが多く、ヒジャブNGとされる場合があります。このような条件は求人情報に明記し、送り出し機関を通じて面接の際に確認することが求められます。企業が事前にできることとできないことを明確にすることが、ミスマッチを防ぐ第一歩となります。
さらに、外国人材に日本への理解を深めてもらうことも重要です。特定技能雇用では、生活全般や就業に関する支援が義務付けられており、生活オリエンテーションとして8時間以上の研修を行うことが定められています。銀行口座の開設や転入届の手続きなどをサポートしながら、日本の生活マナーやルールについて指導することが一般的です。
こうした基本的な支援のほか、ミスマッチを防ぐ取り組みの一例として、定期的な飲み会や会食に合わせて日本語勉強会を実施している企業もあります。こうした活動は、外国人材との交流を深めると同時に、企業文化への適応を促します。受け入れ企業には、ミスマッチやギャップを生まないようにする努力が求められており、外国人材との信頼関係を築くための柔軟な対応が必要不可欠です。
.jpg)
外国人材・日本人従業員双方の理解で活気ある職場環境をつくる
先ほども述べたように、特定技能雇用では、雇用する企業の外国人材への支援が義務付けられており、日本における生活マナーや一般的なルールを外国人材へ伝えることが必要です。こうしたレクチャーは1回だけ実施して理解・浸透するものではなく、折を見て継続することで外国人材が日本で安心して生活することにつながります。
日本人従業員に対しても、外国人材の母国の文化を理解する勉強会を実施している企業の事例は多数見られます。これにより、職場全体の相互理解が深まり、協調性やチームワークの向上が期待されます。
外国人材から日々報告される細かな悩みや相談への対応についても、各国の文化や習慣とのギャップなどの背景を知らないと対応が難しいことがあります。こうした支援対応への準備やリソースが確保できない場合は、登録支援機関への委託によって解決することも一つの手段です。
また、外国人材を雇用する企業内部に向けて特定技能の文化・習慣をレクチャーするサービスも存在するため、企業のリソースに合わせた選択で外国人材との円滑な関係をつくることにつながります。こうした取り組みを通じて、外国人従業員と日本人従業員が互いを理解し、高め合うことで活気ある職場環境の構築が可能となります。
.jpg)
@人事では『人事がラクに成果を出せるお役立ち資料』を揃えています。
@人事では、会員限定のお役立ち資料を無料で公開しています。
特に人事の皆さんに好評な人気資料は下記の通りです。
下記のボタンをクリックすると、人事がラクに成果を出すための資料が無料で手に入ります。
今、人事の皆さんに
支持されているお役立ち資料